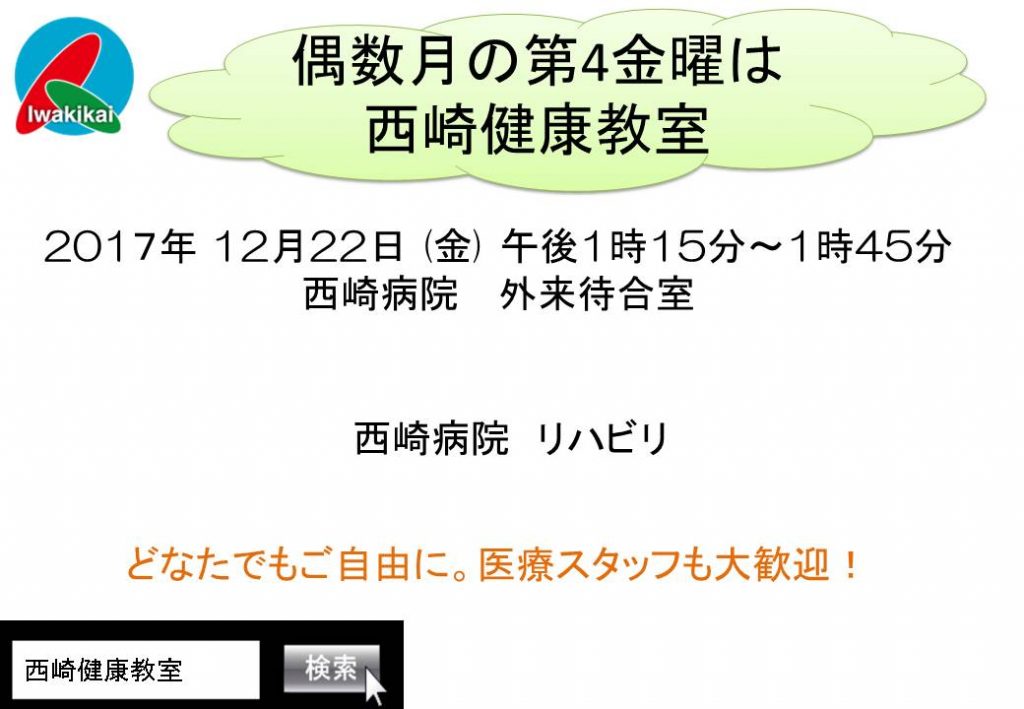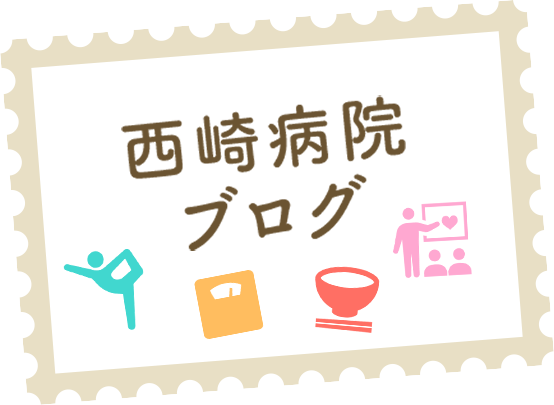チームスタッフの研修会メモより
1、フットケアの基礎知識
最後まで自分の足で歩けるように支援する
足潰瘍の発生原因の69%が靴ずれ、DM患者の下肢切断率は1万人/年で健常者の15~40倍。再発率も高く40~70%/1~3年
2、予防的フットケアの特徴
対象はDMと診断されたすべての患者の足
フットケアの必要性→①足病変の発声を予防②異常の早期発見③重症化を予防し患者のQOLを低下させない④セルフケアへの働きかけ
3、足の解剖生理
足の骨格→200個の骨(全身の1/4を占める)
足のアーチ構造→①足を前に蹴り出す②衝撃を和らげるクッション③足底の筋肉や神経の保護
弯曲が強い→甲高、横アーチのつぶれ→開帳足、内側のアーチの潰れ→偏平足
下肢の静脈→心臓に戻る際逆流を防ぐ弁の役割を果たしているのが静脈弁
下肢の動脈→DMの下肢動脈硬化は両側性で広範囲に生じる、ふくらはぎの部分の動脈閉塞が多い
4、足病変予防の為の検査
①神経障害
知覚神経:怪我に気がつきにくくなる→モノフィラメント
運動神経:歩き方が変わるので怪我や胼胝の原因になりやすい→音叉、アキレス腱反射
自律神経:血流低下により汗が出なくなり乾燥する→心電図RR間隔変動、起立性低血圧
「糖尿病性神経障害を考える会」診断基準を参考にすると良い
②血流評価
皮膚温:足全体の冷感、左右差
脈拍触知:足背動脈、後脛骨動脈の触知、左右差
色:チアノーゼの有無、爪の色
疼痛:疼痛の有無、左右差、挙上時と下垂時の疼痛の違い
他に画像診断(ABI、TBI、SPP、MRI、頚動脈エコー)、感染評価がある
5、足病変
・角化症
胼胝:圧を受けた深部に角質のトゲ状に入り込み痛みを伴う
鶏眼:慢性的に圧を受けた部分の肥厚、痛みは伴わない
・白癬
・爪の異常
巻き爪:爪が横方向を向いている
陥入爪:爪の角がトゲのように軟部組織に刺さり炎症を起こした状態
6、リスクの高い患者
足の潰瘍・壊疽や下肢切断の既往がある
腎不全や透析中
閉塞性動脈硬化症など末梢循環障害がある
糖尿病神経障害が高度
足指や爪の変形、胼胝がある
血糖コントロールが不十分
視力障害が高度でセルフケアが不足
外傷を受ける機会が多い
一人暮らしの高齢者だったり、足の衛生保持が不十分
足病変自体を知らない
喫煙者
7、足病変予防の為のセルフケア
①清潔を保つ:
②乾燥・蒸れを防ぐ
③皮膚の圧迫・ズレを防ぐ
④血流を保つ
⑤危険を避ける
8、フットアセスメントをするために
①手で触る→角質部や足の温度、動脈の確認
②見る→胼胝、鶏眼、傷、白癬の有無。足や爪の色の確認
③嗅ぐ→浸出液や創部の臭いは?

自身がDMチームに参加している為、興味はあるがなかなか学ぶ機会がなかった内容だったので、とても有意義な研修となった。
DMとフットケアは切り離せないもので、基本の観察の仕方やセルフケアまでを含めた患者との関わりを学ぶことができた。
アセスメント方法のグループワークでは、他の参加者と考えることで自分にはない視点や観察眼を知ることができ、現場に沿った内容を学べた。
爪切りの実技では、自分の想像以上に正しいとされている爪の長さがしっかりとあって、実際に確認することができたのが良かった。
フットケアは糖尿病ケアの基本となるので、自身観察眼だけでなく、患者自身が主体的に取り組めるように働きかけていきたい。
西崎健康教室を開催しました。今回のテーマは「バランスの良い食事ってなに?」担当は西崎病院栄養課ということで、栄養素や、献立のたてかたについて、わかりやすく説明していただき、とても参考になりました。次回は12月22日(金)を予定しています。テーマは「リハビリ」なので、ジャージで参加されるといいいかもよ?とのことです(・∀・)!