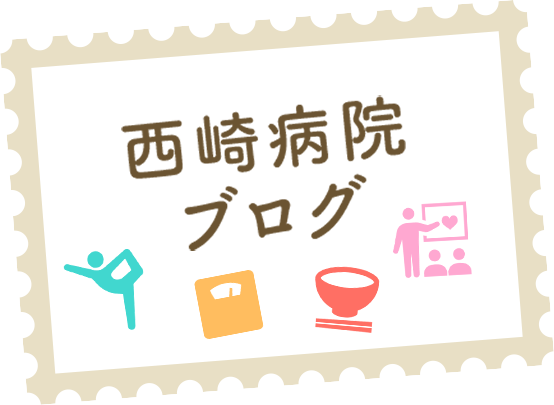内科学会誌の2016年4月号が「内分泌・代謝疾患の救急~初期対応のポイント~」という特集のまとめです。
低血糖性昏睡
●重症低血糖を来す非糖尿病患者の基礎疾患は、低栄養、アルコール中毒、胃切除後、感染症など。
●低血糖でのグルカゴン反応は、2型糖尿病でも長期的には失われ、主としてアドレナリン分泌が血糖上昇に関与する。
●低血糖を頻回に起こしたり、慢性的にゆっくりと低血糖が出現した場合、無自覚性低血糖が起こる(HAAF;hypoglycemia-associated autonomic failure)。
●健常人では空腹時でも70mg/dl以下にはほとんどならない。従って症状の有無にかかわらず、血糖70mg/dl以下は低血糖として対処。
●糖尿病薬以外の低血糖を起こしやすい薬剤 シベンゾリン、ニューキノロン、ARB、否定形向精神薬、ST合材(西崎病院ではバクトラミン)など。
●低血糖性昏睡になって数時間上経過した場合は脳浮腫の可能性あり、90分以上経過している症例にはグリセオール(果糖含有)の投与も考える。

アメリカ糖尿病学会、内分泌学会共同の糖尿病低血糖に関する指針(2013)
blog.livedoor.jp/blogiinkai-tounyoubyou/archives/17163439.html
低血糖関連自律神経障害を改善させるアプローチ(表1)
血糖測定をして血糖を調節
●自己血糖を、食前、眠前、何かおかしい時に測る。
●週に3回は、午前2時と5時にも血糖を測る。
●食前血糖値を100~150mg/dlになるように調節する。
患者教育
●無自覚性低血糖がさらに低血糖の再発を起こすことを教える。
●低血糖を避けることが、無自覚性低血糖をなくす事につながることを教える。
●早期の低血糖症状にきちんと反応して対処するのが大事であることを教える。
食事介入
●適切なカロリーを摂取する。
●食間と寝る前のおやつを勧める。
●ブドウ糖をいつでも手元に置いておく。
●もし飲めるなら、適度なキサンチン飲料を考慮する。
運動カウンセリング
●運動前、運動中、運動後に自己血糖測定をする。
●血糖が140mg/dl以下なら、運動前にカロリー摂取する。
●運動中、運動後にも血糖が140mg/dl以下なら、カロリーを追加する。
治療法の調整
●インスリンの量を目標血糖値になるように調節する。
●食間の低血糖予防のために、ノボラピッド、ヒューマログ、アピドラなどの超速効型インスリンを使用する。
●夜間の低血糖予防のために、ランタス、レベミル(+当院ならトレシーバ)の基礎インスリンアナログを使う。
●必要に応じてインスリンポンプによる持続注入(CSII)を考慮する。
●持続血糖測定(CGM)を考慮する。
その他、低血糖と運転に関連する資料
www.dm-net.co.jp/calendar/2013/020463.php
低血糖と運転免許 安全に運転するための7ヵ条
www.jds.or.jp/modules/education/index.php?content_id=38
無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く)」を呈するおそれがある患者の自動車運転に関する医師のための文書
高血糖緊急症
患者教育(糖尿病の患者さん向け)
●カゼや嘔吐下痢の時(シックデイ)は、主治医に連絡し、指示を受ける。
●インスリンの自己中断は絶対にしてはいけない。
●十分に水分を摂取して脱水を防ぐ。
●食欲のないときは口当たりがよく消化の良いもの(おかゆ、アイスクリームなど)を摂取し、なるべく絶食にならないようにする。
(以上 内科学会誌より参照)
糖尿病性ケトアシドーシス
●血糖値が300mg/dl程度でも起こりうる。
●倦怠感、悪心嘔吐、腹痛などの症状あり。脱水の割にはNa低値、K高値。
●標準治療:最初の1時間で生食500~1000ml。その後は尿量を見ながら200ml/時程度。
●インスリンは超即効型または即効型5単位程度を静注後、5単位/時間程度で持続静注。1時間で血糖が100mlg/dl以上下がらないようにする。
●血糖値が300mg/dl程度になったらカリウム含有輸液に(西崎病院ではソルデム3A)。低カリウム注意。
●1日の総輸液量は5リットル以内に収まることが多い。
高血糖浸透圧症候群
●血糖は600mlg/dl以上が多い。脱水が病態のメイン。インスリンとともに脱水の治療を。